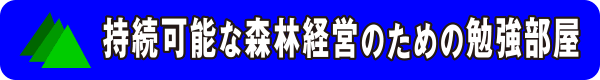 |
| 人と自然を未来に繋ぐ「しもかわチャレンジ」-林政ジャーナリストの会共同取材から(1)(2025/7/17→8/14改定) | ||
|
|
||
|
2008年環境モデル都市_選定、2011年環境未來都市_選定、2017年 第1回ジャパンSDGsアワード_「SDGs推進本部長賞」受賞、2018年SDGs未来都市_選定 このように、国が主導する、「世界の先導となる低炭素社会への転換」(環境モデル都市の選定趣旨)、「中長期を見通した持続可能なまちづくりに向けて・・・経済社会環境の三側面をつなぐ統合的取組における相乗効果、新しい価値の創造を通じて持続可能な開発に取り組む自治体を支援」(SDGs未来都市について)、といった取組の第一線で、森林都市の取組をリードしてきた下川町です。 町長はじめスタッフの皆さんから「持続可能な地域社会の実現に向けて~人と自然を未来に繋ぐ「しもかわチャレンジ」という演題でお話をいただきました。その内容を中心に紹介しますネ この原動力はなにだったか? ((下川町のバックグラウンド)) 下川町SDGs未來都市計画のイントロに「地域特性」というセクションがあり、わかり易く説明しています。それに沿ってすこし背景と歴史を紹介します ーーーー (下川町のチャレンジの背景)
こうした幾多の危機や困難に対して、下川町民は知恵、工夫、行動で立ち向かい、乗り越え、発展してきたが、この過程において、他の自治体には無い独自の地域特性である「しもかわイズム」が形成され、2000 年代には、「経済、社会、環境の調和による持続可能な地域社会づくり」のコンセプトが生まれ、これまで約20 年以上に渡り取組みを進めてきました。(のだそうです) (チャレンジの内容)
地域資源である森林を最大限・最大効率に活用することを基本とし、持続可能な森林経営システムである「循環型森林経営」(環境モデル都市下川町行動計画のコンセプト)を基軸として、①森林総合産業(林業・林産業・森林バイオマス産業)の構築(森林総合産業特区地域活性化方針(20211総理大臣))、②超高齢化社会にも対応した新たな社会システムの構築、③森林バイオマス等の再生可能エネルギーを活用した地域エネルギーの完全自給と低炭素社会構築、を柱とした経済・社会・環境の三側面の価値創造、統合的解決による「持続可能な地域社会(森林未来都市)の実現」に向けた取組みを進めています。(以上第3期下川町SDGs未来都市計画(p2 「将来ビジョン」地域特性)から) そして、今後以下のようなチャレンジをしいく、としていますが、関心ある方は第3期下川町SDGs未来都市計画(p7などを是非ご覧ください) 「2030 年における下川町のありたい姿(下川版 SDGs)」 7つの目標 ーーーーー
その結果、どんな集落になっていくのか、具体的な事例を見てみましょう。 中心市街地かから12キロ離れた「一の橋地区」 めざすべき姿:超高齢化問題と仮炭素化を同時解決 太陽光パネル(15kw)木質ボイラー(550kW)新設におる、集住化施設障碍者支援施設などに対する熱供給(右の図→) (地域おこし協力隊) 限界化する集落再生を目的に「地域おこし協力隊」を導入
活動内容:廃屋の撤去、ICT見守り、ハウス栽培、石窯ピザ販売、商品開発、生活・買い物支援、除雪、地域食堂運営、機能性植物栽培、環境保全、障がい者施設支援、集落支援型NPO法人支援、施設管理・水源管理 その結果65才以上の人口の割合が、2009年に52%だったのが、2021年には30%に (農林水産省のサイトに農村の日常生活を支える機能の集約とネットワークの強化 取組事例 ①北海道下川町(一の橋地区)というわかり易い解説ページがあります) 以上が町長以下スタッフのプレゼン内容の概要です ーーーーー
もう一つの下川町の森のトピックスが、下川町が2003年に北海道で一番早く(日本で12番目)くFSC森林認証を取得したことです。 なぜ、下川町で早いうちに森林認証の取組が進んだのでしょうか? FSCのサイトに下川町森林組合というページがあり解りやすい解説があったので、紹介します。 下川町森林組合片岡事業部長(当時?)のお話です (FSC認証のきっかけ) 下川町が2003年、FSC/FM認証を取得した当時、国内では、海外での森林破壊や違法伐採材が注目され、木材生産主眼を置いた国内の林業基本法が、「環境」というキーワードの盛り込まれた森林・林業基本法へと改正された時期でした そうした背景もあって、もしもこの町の林業が衰退したら、この町がなくなるのではないかという危機感が自治体や町民の中で生まれました 。「そこで、下川町をはじめ森林組合や商工会、木工所、学校連合、道の出先機関、消費者などが集まり、『下川小流域管理システム推進協議会』を立ち上げて、下川町の林業をこの先どうするか考えることになりました ちょうどその頃、国内ではFSC認証というものが西日本方面で認証取得に向けた動きが始まってきたタイミングででした。 講習会や講演会を通じて森林認証についての情報を収集して、協議会で話し合いを進める中で、地域の林業が適正な国際ルールの下で展開していかないと通用しないのではないかという話になりFSC認証取得に取り組むことになりました。(なのだそうです) (下川町のFSC支援事業) 「例えば認証林ではない山で作業をするとき、その山の所有者にグループ認証に参加すればFSCの基準で手入れをして、施業の費用には町から助成金が出ますよと説明する。すると直ぐに同意書にサインしてくれるのです」。 10年ほど前から始まったこの下川町独自のFSC支援事業のおかげで、私有林の所有者は少ない自己負担で森林の手入れを行なうことができるようになっています。 この制度のおかげもあり、現在でもFSCへの参加はふえており、森林組合が生産する材はすべてFSC材になっている、(のだそうです)。 ーーー もう少し、FSCのページを内容をかいつまみます ーーーー しかし、これだけの手厚い補助制度を整備するだけのメリットを、町として見出せるものなのであろうか。 この問いに対して片岡さんは、下川町全体の森林整備が行き届くことがメリットだと言い切る。 以上がFSCの取り組み内容です(FSCのページの内容が丸投げで、ごめんなさい (先住民との関係) 町長の説明の中に、「1901年岐阜県から入植」というお話があったので、その時先住民との関係はどうだったのですか?と伺いました。 そうしたら、「上名寄の開拓」という文書を紹介いただき、以下のような記載を紹介いただきました(ほんの一部です)
こんな歴史がFSC認証原則3の先住民の権利の中で、どのように反映されているかな? 興味があったので聞いてみました。そして調べてみました。 すると、アイヌの人々および関係団体の皆様へ(上川森林認証協議会/下川小流域管理システム推進協議会)というページがあり、以下の情報が発信されています
どんな意見があったのかな? 今後の展開をフォローしていきますね ((しもかわチャレンジShimokawa Challenge)) 少し長くなりましたが、しもかわチャレンジの内容を①持続可能な開発目標(SDGs)と、②持続可能な森林の第三者認証FSCの二つにわけて、見てきました。
まだまだ、課題はたくさんあるんでしょうが、是非、しもかわチャレンジが、Shimokawa Chellengeとして、世界中に発信されるようになったらいいですね。 御手伝いできれば・・・ kokunai10-7<simokawaCHL> |
|
■いいねボタン
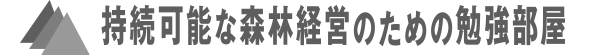 |