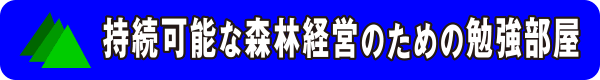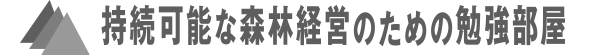|
 7月10日に投票が行われた第27回参議院選挙。 7月10日に投票が行われた第27回参議院選挙。
自民党と公明党が参議院でも過半数がとれず、既成政党でなく新たな党が力を持つ。
大きな国政選挙は各党の政策力が現れる場です。
恒例となっている、各政党の政策での森林と林業分野の記載状況を、チェックしました。
目次
自由民主党/ 公明党/ 立憲民主党/ 日本維新の会/ 国民民主党/ 日本共産党/ れいわ新選組/ 参政党
保守党/ 社会民主党
ーーーーー
自由民主党
選挙公約日本を動かす暮らしを豊かに
総合政策集2025Jファイル
□震災復興
315 林業の再生とふるさとの恵みの回復
震災以降、荒廃した森林の再生を進めるため、帰還困難区域内における森林整備の再開に向け、作業者の安全確保や整備対象の把握、木材検査方法の見直しなど、必要な条件整備を進め、間伐や路網整備など具体的な目標を定めて本格的な復旧に着手します。その際、地元自治体や森林関係団体と連携し、丁寧なリスクコミュニケーションに努めます。
併せて、「ふくしま森林再生事業」や「里山・広葉樹林再生プロジェクト」など、川上から川下までの一体的な取組みを継続し、原木・原木しいたけなどの産地再生を推進します。更に、大阪・関西万博での木材活用の例に倣い、中高層の公共建築物において福島県産材の利用を広げるため、各省庁間での建築予定や製品情報の共有を進めてまいります。
□農林水産
481 自然災害からの復旧・復興と防災・減災、国土強靱化のための緊急対策
近年の豪雨、地震等、頻発する自然災害に対し、被災した農林漁業者の一日も早い経営再開に向けて、農地等の復旧や農業用ハウスの再建等、きめ細やかな支援対策を継続的かつ迅速に講じます。
防災・減災、国土強靱化のため、「ため池工事特措法」に基づく防災工事等を推進し、また、第1次国土強靱化実施中期計画のもと、農業水利施設等の老朽化対策や田んぼダム等の流域治水対策、農業用ハウスの補強、山地災害危険地区等における森林整備・治山対策、漁港施設の耐震・耐津波・耐浪化等を加速して実施します。
482 東日本大震災、能登半島地震等に係る農林業再生等に全力
・・・
帰還困難区域内の森林整備の再開に向けて、森林作業のガイドラインの策定や、木材検査体制を含む必要な運用等の見直し、リスクコミュニケーション等に取り組みます。
また、福島等の森林・林業・木材産業の再生に向け、引き続き、「ふくしま森林再生事業」や良質な原木や原木しいたけ等の産地再生に向けた「里山・広葉樹再生プロジェクト」、「里山再生事業」等、川上から川下までの取組みを進めます。
・・・
令和6 年能登半島地震および豪雨について、地域の将来ビジョンを見据えて、農林漁業者の一日も早い生業の再建や世界農業遺産「能登の里山里海」等のブランドを生かした創造的復興に向け、被災した棚田等の農地や農業用施設、畜舎、林地・林道の復旧・復興等、生業再開に向けた支援を全力で進めます。
岩手県大船渡市等の大規模林野火災について、森林復旧や生業再建の取組みを進めます
494 鳥獣被害対策・ジビエ利用の推進
鳥獣被害対策に全力で取り組みます。暮らしや農林業に深刻な被害を及ぼすシカ・イノシシ・クマ・サル等の野生鳥獣による被害を防止するため、地域ぐるみでの「捕獲」「侵入防止対策」「生息環境管理」の総合的な対策を推進するとともに、捕獲鳥獣のジビエ活用の一層の拡大に向け、捕獲から消費までの各段階の課題に応じた対策を講じます。・・・森林・林業においてもシカによる被害が深刻化しており、効果的・効率的なシカ捕獲の取組みを関連事業と連携して推進します。
501 森林・林業・木材産業によるグリーン成長の実現
2050 年ネット・ゼロの実現に向け、改正森林経営管理法に基づき、再造林等に取り組む林業経営体に対し、森林の集積・集約化を進める新たな仕組みの活用を促進するとともに、路網の整備や高性能林業機械の導入、再造林の省力・低コスト化、エリートツリーの安定供給、加工流通施設の整備、スマート林業実装加速化の、
労働力確保に取り組むとともに、針広混交林等の森林づくり、森林病害虫対策、林野火災対策等による森林資源の適正な管理と林業・木材産業の持続的発展を推進します。
502 森林吸収源対策の推進
パリ協定を踏まえ、森林吸収源対策を推進します。2050 年ネット・ゼロの実現に向け、「伐って、使って、植えて、育てる」森林資源の循環利用の確立を図るため、国産木材利用の拡大等の取組みと併せて、路網整備、植林、下刈りや除伐・間伐等に支援する森林整備事業を推進していきます。
地域の森林整備の促進にも貢献する公的主体
による奥地水源林の適切な整備、林業公社の経
営改善の支援を図ります。
503 森林の経営管理の集積・集約化
森林の循環利用を着実に進めるため、改正森林経営管理法に基づき、伐採だけでなく、再造林等に取り組む林業経営者に対し、森林の集積・集約化を進める新たな仕組みの活用を促進します。
また、森林環境譲与税等を活用して路網整備・間伐等の森林整備の更なる推進を図るとともに木材の需要拡大等を進めます。
更に、森林経営管理制度を円滑に推進するためには、担い手の中核となる林業経営者の育成が重要であるため、国有林野の一定の区域で、公益的機能の確保や地域の産業振興等を条件に、一定期間・安定的に樹木を採取できる樹木採取権制度の活用を図ります。
施業集約化、外国資本等による森林買収の防止等を図るため、森林法や森林経営管理法も活用し、林地台帳情報の充実、森林所有者に対する経営管理の意向調査、ICT
活用による森林情報の整備や境界明確化、地籍調査等を加速化推進します。
504 スマート林業・DX の推進
スマート林業・DX を推進し、林業経営体の経営の安定化、林業従事者の所得や安全性の向上、省力化を図ります。特に、プラットフォームの構築・運営を通じて、林業機械の自動化・遠隔操作化及び森林内の通信環境確保に向けた開発・実証、新たな技術を活用した革新的な林業に取り組みます。
また、地域一体となって森林調査から原木の生産・流通に至る林業活動にデジタル技術をフル活用する「デジタル林業戦略拠点」の構築を進めます。
505 林業を支える多様な担い手・人材育成「緑の雇用」や緑の青年就業準備給付金により若い新規就業者の確保と定着を図り、森林総合監理士(フォレスター)、森林プランナー、オペレーター等林業技術者・技能者の育成を推進するとともに、外国人材の受入れに向けた取組みを推進します。また、森林組合、林業事業体、自伐林家など多様な担い手の育成、造林に係る林業経営体の新規立ち上げのほか、労働安全強化対策等を促進します。
506 国土強靱化に向けた治山・森林整備対策
地球温暖化の影響により、線状降水帯の発生等による山腹崩壊等が多発している中、災害リスクに対処し、国民の安全・安心な暮らしを実現するため、能登半島地震や豪雨等による被害を受けた荒廃山地の復旧対策の着実な実施、山地災害で得られた教訓を踏まえた治山対策の推進、森林資源の循環利用や花粉症対策にも資する強靱で災害に強い林道の整備、主伐後の確実
な再造林や間伐等を推進します。また、治山施設、林道施設等の長寿命化に取り組みます。
特に早急に治山対策や森林整備等が必要な危険地区等において、5 か年の加速化対策を計画的かつ着実に実施するとともに、第1次国土強靱化実施中期計画のもと、森林整備・治山対策を進め、緑の国土強靱化を推進します。
507 国産材の安定供給体制の構築
円安の影響等による輸入量の減少、SDGs への企業意識の高まりなどの機会を捉え、国産材の利用拡大を進めるとともに林業・木材産業の体質を強化し、川上から川下までを含めた総合的な対策を講じます。具体的には、レーザ計測機器等の導入を含めた路網の整備、高性能林業機械の導入、再造林の省力・低コスト化、木材加工流通施設の整備、急傾斜に対応した架線系集材技術の開発・普及、伐採と造林の一貫作業システムの導入、コンテナ苗の活用等により、生産基盤強化を進めるとともに、国産材への転換を進める製材業者や工務店等による効率的なサプライチェーンの構築や木造公共建築物の整備等、非住宅分野をはじめとした木材の消費拡大を進め、成長の主役である地方経済における主要な産業の林業・木材産業を下支えします。
508 花粉症対策の推進
花粉症ゼロ社会を目指します。「初期集中対応パッケージ」に基づきスギ人工林の伐採・植替えの加速化、スギ材の需要拡大、花粉の少ない苗木の生産拡大、花粉飛散防止剤の開発・実用化などを推進します。
509 「都市(まち)の木造化推進法」に基づく国産木材利用の拡大
森林・林業・木材産業によるグリーン成長を実現し、森林所有者や原木の生産者の所得の増大と地域の雇用の拡大を進め、山村の振興を図るため、国産木材の自給率5
割を目標に木材の利用拡大に総合的に取り組みます。
①住宅における木材利用
国産材需要の約半分を占める住宅分野において、梁や桁など国産材の利用が低位な部材での国産材シェアを高めるとともに、工務店と林業・木材産業関係者の連携による国産材を活用した住宅づくりを推進します。
②非住宅・中高層分野等における木材利用
「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」(通称:都市(まち)の木造化推進法)に基づき、公共建築物(学校など)における木材利用の徹底と支援を行うとともに、国又は地方公共団体と民間事業者の間で締結する建築物木材利用促進協定により、民間建築物における木材利用を促進します。
③国民運動による木材利用の促進
心理面・身体面の効果など木材の良さを発信するとともに、国民運動としての木材利用促進に取り組みます。
510 JAS 構造材やCLT 等を活用した国産材需要拡大
建築物への木材利用促進に当たっては、大半が非木造構造である中高層建築物を中心に、JAS構造材やCLT(直交集成板)、耐火部材等を含めた技術開発や設計者・施工者の育成に取り組みます。
511 合法木材の利用促進
改正クリーンウッド法(合法伐採木材等の流通及び利用の促進に関する法律)に基づき、木材関連事業者による合法性確認等や合法伐採木材の利用を徹底するとともに、木材生産国における関連制度等の把握を進めるなど、地球温暖化防止等に資するための合法伐採木材の利用促進に向けた取組みを強力に推進します。
512 国産木材の輸出促進
農林水産物・食品の輸出拡大実行戦略に基づいて、木材の輸出を推進します。特にジャパンブランドの確立や日本産木材製品の認知度向上、輸出先国の規格・基準に対応した加工施設等の整備等を通じて、海外市場で求められる付加価値の高い木材製品の輸出拡大を進めていきます。
513 木質バイオマス利用の促進
山村地域の雇用と所得の拡大、山元への還元を確実にし、山村地域の活性化を図るために、地域の関係者の連携のもと、熱利用または熱電併給により、森林資源を地域内で持続的に活用する「地域内エコシステム」を構築し、木質バイオマスのエネルギー利用を促進するとともに、改質リグニンやセルロースナノファイバー、木の酒などのマテリアル利用を積極的に促進します。
514 山村振興対策等の強化
森林の多面的機能の発揮を支える山村の地域活動や林家の取組み(森林の管理、侵入竹への対応等)を総合的に支援します。
また、「改正山村振興法」を踏まえ、山村の自立的かつ持続的な発展を促進するため、地域資源の活用による産業振興に向けた交付金等により、山村活性化の支援を推進します。
きのこ、薬草、木炭など特用林産物は、農林複合的な収入確保に資する重要な地域資源であり、需要拡大や生産性向上、輸出拡大等を図ります。加えて、健康・観光・教育など様々な分野での森林空間の活用をはじめとした森業を推進します。また、その一環として、J-クレジットの普及拡大に向け、森林由来クレジットの創出と幅広い企業等の需要拡大に取り組み、持続的な林業経営への貢献を図ります。
515 国民参加の森林づくりの推進
森林・林業への国民理解の醸成、木材利用の促進の観点等も踏まえ、植樹活動等の国民運動を展開します。企業やNPO のネットワーク化などを進め、多様な主体が参加した森林づくりを推進します。
□環境
644 生物多様性保全に向けた国際的リーダー
シップの発揮2022 年のCBD COP15 で採択された「昆明・モントリオール生物多様性枠組」の着実な実施に貢献すべく、生物多様性国家戦略2023–2030
を推進します。特に、陸地及び海洋の30%以上を保全する30by30 目標の達成に向けて、国立・国定公園の拡充やOECM(保護地域以外で生物多様性保全に資する地域)の設定・管理を進めます。併せて、森林やブルーカーボンを含む吸収源の確保や気候変動適応にもつなげ、日本の国際的な役割を強化します。
645 生物多様性に関する情報基盤の整備・発信
ネイチャーポジティブ目標の達成に向けて、ネイチャーポジティブ経済への構造転換を進めるには、生物多様性に関する正確で信頼性のある情報の整備と発信が不可欠です。
このため、国、地方公共団体、企業、市民、研究機関など多様な主体が生物多様性に関する情報を利活用できるよう、情報の把握・整備の迅速化を図るとともに、データの標準化やオープンデータ化を推進し、社会全体での共有と利活用を促進します。
646 ネイチャーポジティブ経済の実現
TNFD(自然関連財務情報開示)による自然関連情報の開示は、企業が自然資本の保全・回復に責任ある行動を取るための基盤となり、ネイチャーポジティブ経済への転換を支える枠組みです。官民が連携してこの枠組みの活用を積極的に進めることで、サプライチェーンの強靱化や自然に配慮した新たなビジネスの創出を促進し、企業のネイチャーポジティブ経営への移行を推進します。併せて、ネイチャーポジティブに関連する国際的ルール形成にも主体的に参画し、日本の特性を反映した制度設計を働きかけていきます。
647 豊かな自然環境を維持し取り戻す仕組みづくり
鎮守の森の保全や里山の再生、生物多様性の確保、生態系サービス(水源涵養、防災・減災、食料供給など)の維持を目指し、「地域生物多様性増進法」に基づく自然共生サイトを2026
年度までに500 以上認定し、地域、企業、市民団体など多様な主体の取組みを促進します。相続税・贈与税の評価減措置などの税制支援も活用しながら、こうした活動を地域に根付かせ、人口減少などの社会状況を踏まえた持続可能な自然環境の保全・再生を通じたネイチャーポジティブな地域づくりを進め、SATOYAMA
イニシアティブ等を通じて海外へ発信します。また、今後のまちづくり・インフラ整備においても、人と自然が共にあるコンパクトで環境にやさしい地域づくりを進め、都市機能と自然が共存する持続可能な生活空間の実現をめざします。
|
公明党
2025参院選重点政策
5.活力ある地域づくり
⑧魅力ある農林水産業の構築
●国民病とも言われる花粉症問題の解決に向けて、スギ人工林の伐採・花粉の少ない苗木への植替え等を通じた花粉発生源対策、花粉の飛散を抑える技術の実用化、花粉症緩和米に係る研究開発を加速します。
●森林資源の循環利用を促進するため、林業経営体への森林の集積・集約化の促進に加え、エリートツリー等の苗木生産施設・加工流通施設・路網の整備や、高性能林業機械の導入、間伐や再造林対策、輸出を含む新たな需要の創出等を総合的に支援します。
●木材需要の拡大に向けて、製材・CLT(直交集成板)・LVL(単板積層材)等の建築物への利用を後押しするとともに、非住宅・中高層建築物等の木造化・木質化、内装・家具等における需要拡大を推進し、木材利用を促進するための国民運動を着実に進めます。
●地域の有効的な資源である木質等のバイオマス活用を推進するため、プラント等の施設やバイオ液肥の散布車、災害時のレジリエンス強化に必要な機械の導入等を支援します。また、国産バイオマス燃料の安定供給実現に向けた支援を行います。
|
立憲民主党
立憲民主党政策集2025 あなたを守り抜く8つの政策
【環境】
(生物多様性)
〇海外から流入し日本の木材市場に悪影響を及ぼす違法伐採木材を日本の市場から排除するため、合法性の確認を徹底する仕組みや、違法伐採木材である可能性を否定できない木材流通の在り方について検討します。
【農林水産】
(森林・林業政策)
〇適切な森林管理の支援、国産材の安定供給体制の整備などにより、「木材自給率50%」を目指します。適正に管理された森林から産出した木材を認証する制度を推進し、違法伐採木材の国内流通を阻止する実効性ある施策の検討を行います。
〇花粉症対策として、無花粉・低花粉の苗木の生産拡大を進め、建築分野における需要創出策とともに、伐採加速化計画を策定・実行します。花粉飛散防止剤の実用化等を進めます
|
日本維新の会
維新八策2025個別政策集
地方活性化
56.地方において高速インターネットを不自由なく使える環境を整備し、企業の社員がワーケーションを行ったり、農林水産業を副業で営める仕組みをつくることで、交流人口の拡大や定住へとつなげます。また、希望する高校生や大学生が一定期間農山漁村にファームステイし、地方が豊かな国土の保全や食料確保という重要な役割を担っていることを若者に啓発するとともに、過疎地の活性化を図ります。
農林水産
262.
人口減少や担い手不足等に対応して、重労働である農作業を可能な限り省力化し、同時に生産性の向上をもたらして農林水産業の成長産業化に資するスマート農林水産業の展開を図ります。具体的にはドローンや各種無人機、AIなどの先端技術の開発を支援し、新しい試みにチャレンジできる生産現場の確立を目指します。
274.
国産材の需要拡大を図るため、森林バンク法の積極的な活用により、国産木材の積極的な活用を支援し、森林の適正な保全に繋げます。
275.
キャンプ、マウンテンバイク等、森林の利活用による収益化を進め、環境と共存した中山間地域における経済の発展を図ります。 |
国民民主党
政策パンフレット
2 自分の国は自分で守る
1防災・減災対策強化
(9) 国土柔軟化政策
温暖化による水害多発時代を踏まえ、ダム等の施設だけに頼らない、士地利用配慮や森林保全、避難態勢づくりを含む「流域治水」を国・自治体・企業・住民等が連携して進めると同時に、生物多様性を埋め込んだグリーンインフラを増やす国土柔軟化政策を進めます。
P21
3 「総合的な経済安全保障」の強化
(2) 国民全体で農山漁村を支える循
珊型社会の構築
②宝の山を未来につなぐ
■国産材でつくる持続可能な社会
戦後に造林した木材の多くが伐採期を迎えており、国産材の供給余力は増加している一方、未だ国産材利用率が低いのが現状です。
農業用ハウスや畜舎、木質サッシの推進を含め住宅、公共建築物等への木材利用を加速させ、森林資源の有効活用により持続可能で地球温暖化防止に寄与する林業に転換し、国内林業を活性化させます。
■山を守る、育む
「伐って、使って、植xる」ルールを徹底(間伐と主伐後の再造林の義務化と、伐採届け出の厳格化)します。
適切な森林管理に対する直接支払いの充実を図り、防災や水資源の確保の観点から森の保全に努めるとともに、林業従事者の安全を確保した労働安全環境を構築する施策を行います。
■花粉症対策
国民の約3割以上が罹患しているスギ花粉症の対策強化を因るため、スギ人工林の伐採•利用・植え替えの促進、花粉の少ない苗木の生産拡大、花粉飛散抑制技術の開発をさらに進
めます。 |
日本共産党
2025年参議院選挙各分野別政策38、森林・林業
各分野の政策
38、森林・林業
政府の「林業成長産業化」路線を転換し持続可能な林業をめざします
2025年6月
我が国の森林は、国土面積の3分の2を占め、木材の供給とともに国土・環境の保全、水資源の涵養、生物多様性など公益的な機能を有し、国民生活に不可欠な役割をはたしています。またCO2の吸収・固定による地球温暖化防止への寄与など「低炭素社会」の実現にも欠かせない資源です。
この大事な役割をもつ森林を歴史的に維持・管理してきたのが林業です。我が国の林業はいま、歴代政権の外材依存政策のもとで木材価格の低迷が続き、林業労働者が減少するなど、危機に瀕しています。それに拍車をかけているのが、自公政権による林業の「成長産業化」路線です。森林の多面的な機能を著しく軽視し、大規模化した合板・集成材企業やバイオマス発電企業に安価な木材を大量に供給することを優先したもので、森林所有者の「成長」ではありません。国有林・民有林問わず、植林後約50年(標準伐期齢)の森林を大規模に皆伐(一斉伐採)を推進していますが、伐採後の再造林はすすんでいません。
政府は、2021年6月「森林・林業基本計画」を改訂し、「成長産業化」からカーボンニュートラルに寄与する「グリーン成長」に変更しましたが、実態を無視した経営規模拡大の推進など「成長産業化」路線を推進するものとなっています。森林所有者や林業関係者からは、大量伐採による木材生産は供給過剰を作り出し、ただでさえ安い木材価格をさらに引き下げ、自然破壊をおしすすめるものだと批判が高まっています。
政府は、標準伐期(約50年)での伐採は、森林の循環を作るうえで妥当としています。しかし、50年程度の森林はなお成長する若い森林であり、150年前後まで成長が続き、多面的機能も向上すると指摘されています。標準伐期齢での主伐は、多面的機能発揮にも反し、再び資源を枯渇させ、優良な資源づくりを放棄するだけでなく、資源の再生を困難にさせます。
いま必要なのは、安価な木材を大量供給する「成長産業化」路線を転換し、持続可能な森林づくりをすすめることです。国産材の利用と森林の公益的機能の持続的な発揮は、森林・林業者だけでなく、国民共通の願いであり、国際的な合意でもあります。
植林後50年程度で伐採する短伐期一辺倒を見直し、地域の森林資源の実態に対応し、長伐期や複層林など多様な施業方式を導入し、持続可能な林業にとりくみます。
森林生態系や自然環境の保全を最優先する林産物貿易ルールめざす――丸太や製材品などの林産物は、WTO(世界貿易機関)協定では、自動車や電化製品と同じ「鉱工業製品」扱いになっていますが、多くの国が林産業育成や環境保全などのため、丸太の輸出規制を行っており、実質的に自由貿易品目でなくなっています。森林生態系や自然環境は、人間の生存にかかわる問題であり、市場まかせにする時代ではありません。
輸出国主導のWTO体制を見直し、森林生態系や自然環境の保全を最優先する林産物貿易ルール、各国の経済主権を尊重した森林・林業政策を保障することを世界に提起します。
日欧EPA、TPP11が発効により、かろうじて残されていた製材や集成材などの関税は撤廃されてしまいました。
そうなれば、合板・集成材や燃料材などの国内の大規模製材所、木材産業が、国産材価格の引き下げ圧力を強めることは明らかであり、森林所有者と地域経済への影響はさけられません。日欧EPA,TPP11の離脱を要求します。
再造林可能な山元立木価格の実現で国産材の安定供給を確立する――伐採後の再造林が進まず、植林未済地が広がっており、森林資源の再生の妨げとなるだけでなく、水資源や国土環境保全機能の低下など、国民的な問題です。再造林が進まない最大の要因は、費用が確保できないことがあります。林業関係中央団体は、再造林可能な価格の実現めざして合意しています。木材加工メーカーや需要者などとの協議をすすめ、再造林可能な山元価格の実現を目指します。
木材生産は、大型製材工場への供給が優先され、大径材(末口30cm以上)の製材、加工体制が遅れています。大径材の製材の開発、需要拡大などをすすめます。また、木造住宅の構造部材で輸入依存度の高い横架材(梁、桁)を国産材に切り替えていくため、技術開発への支援をはかるなど、国産材の安定供給体制の確立をはかります。
地域の実態に即した産地づくりにとりくむ――わが国の森林は、亜熱帯から亜寒帯まで分布し、植生も多様です。地域ごとに異なる歴史や自然的、社会的条件を持っており、画一的、効率一辺倒な政策ではなりたちません。
林業、素材生産、製材・加工、工務店などが参加する地域の林業振興のための共同のとりくみ(森林管理委員会等)を広げ、地域の実態に即した産地づくりを支援します。
林業の基礎となる林地の地籍調査は4割台にとどまり、事業の障害になっています。地籍調査と境界確定を促進し、地域の森林資源の実態に即した多様な施業方式の導入など地域林業の育成をめざします。
持続可能な森林づくりにとりくむ自伐型林業を支援する――自己所有林や所有者から管理を受託して、間伐や択抜(樹木の抜き切り)を繰り返し、森林資源の蓄積量を増やすとりくみをすすめている自伐型林業が注目されています。自伐型林業は、従来型の大規模林業と違い、多くの林業従事者を生み出しています。現に都市部から、Uターン、Iターンにより人口減少がすすむ中山間地の市町村に移住する、比較的若い世帯が増加しています。森林を活用する「地方創生の鍵」として期待され、73を超える自治体が独自の支援策を講じています。自伐型林業を担い手して位置づけ、森山漁村多面的機能発揮対策交付金の拡充など支援をはかります。
地形や自然環境に配慮した林道・作業道の整備、架線系システムの継承発展にとりくむ――生産基盤となる林道や作業道の路網整備が大きく立ち遅れています。路網整備では、生態系や環境保全に配慮した技術を確立し、災害に強い路網整備をすすめます。昨今の豪雨災害による山地の崩壊の原因に、高性能林業機械による大規模伐採が原因でないかとの指摘があります。山地崩壊をさせない地形や自然環境にあった技術の開発を国の責任ですすめます。また、急傾斜地では、林地保全などから架線集材システムが有効です。集材機の開発や技術者を確保し、技術の継承、発展をはかります。
林業就業者の計画的な育成と定着化の促進、就労条件の改善にとりくむ――林業は、森林の多面的機能や生態系に応じた育林や伐採などの専門的知識や技術が必要です。基本的技術の取得を支援する「緑の雇用」や「緑の青年就業準備給付金」事業の拡充や事業体への支援を強め、系統的な林業労働者の育成と定着化にとりくみます。
また、安全基準などILOの林業労働基準に即した労働条件や通年雇用、月給制の導入など労働条件の改善にとりくみ、安心して働ける環境をつくります。
広葉樹の有効利用をすすめる――広葉樹は、雑木として位置付けられているため、消費の約8割がチップ用となっています。一方で、広葉樹材の輸入困難から家具生産が減少しています。広葉樹材の自給率は、約1割にとどまっています。家具や建築などへの利用をすすめるため、広葉樹資源の調査をすすめ、素材生産や流通体制の整備などへの支援をすすめます。
再造林は適地的木ですすめる――近年、主伐面積が増加していますが、伐採跡地への再造林は、約3割にとどまっています。苗木の供給体制を強化するとともに再造林コストの引き下げにとりくみ、再造林未済地を早期に解消する対策を強化します。国有林・民有林を含め、土壌・適木調査が実施されており、再造林は適地・適木ですすめます。
国産材のカスケード利用にとりくみ、木質バイオマス発電のやり方を改める――良質材から低質材まで建築材や木製品、紙製品、エネルギーなど、100%有効に利用するカスケード利用にとりくみます。
固定価格買取制度で、木質バイオマス発電が一番高い価格がつけられたことに乗じて、大型の木質バイオマス発電所の建設が相次ぎ、製材として利用できる木材まで燃やされており、これでは木材資源の浪費です。国産材の活用となる林業の振興と森林の育成を基本に、それと合致したバイオマス発電を推進します。
災害による山地崩壊や施設被害の復旧に全力でとりくむ――近年、全国各地で地震や豪雨による大量の流木や山地崩壊、施設などの被害が頻発しています。林野庁の災害情報によると、毎年1万ケ所以上の被害が報告されています。荒廃林地や施設被害の全面復旧、流木による二次被害防止対策などにとりくみます。
地域材を活用した仮設住宅や復興住宅の建設に力を入れるなど、地域の森林・林業の再生のとりくみを支援します。
シカ等の野生獣による食害や病虫害害対策にとりくむ――シカなどによる食害やナラ枯れなどの被害は減少傾向にありますが、年間約5,000haに及び生態系の破壊など人間生活にも影響を与えています。野生獣の防除と捕獲、個体数の管理や病虫害の効果的、効率的な防除技術の開発をすすめます。捕獲した野生獣の食肉流通対策を支援します。
特用林産物の振興や都市住民との交流などで就労機会の確保をはかります――きのこや山菜など特用林産物の生産振興や加工・販売などにとりくみ、自然環境を活用したレクリーション,保健・休養など都市住民との交流などのとりくみをすすめ、就労機会の確保をはかります。
市町村や森林組合への支援を強める――市町村は、森林・林業の基本となる「林野台帳」の整備や森林整備計画の樹立をはじめ、2019年の森林経営管理法によって、民有林の経営管理権の設定などが制度化され、地域の森林管理のとりくみが求められています。何よりも森林所有者の意欲を引き出すとりくみが求められています。専任の職員を配置できない市町村も多く、森林・林業行政全般の研修など、林務職員の育成・確保をはかれるよう市町村への支援を強めます。
また、森林組合は組合員の所有面積は私有林面積の7割を占め、地域の森林整備の中心的な役割を担っています。森林組合は組合員の要求をくみ上げ、市町村や地域の素材生産や製材業などと連携し、地域林業の確立のために積極的な役割がはたせるよう支援を強めます。
森林のCO2吸収力を評価した排出量取引で、山村地域と都市部の連携を強める――国内のCO2排出量の削減を促進するために、森林の整備によるCO2の森林吸収量と、化石燃料の木質バイオマスを使うことによるCO2排出量の削減量を評価して、都市部の企業や自治体の排出削減のとりくみにおけるカーボン・オフセット(炭素排出量の相殺)に活用する制度を本格的に導入し、植林・間伐などの森林整備の資金を生み出します。
森林環境税・森林環境譲与税を見直す――森林環境税は、森林経営管理法に基づき、地方自治体が新たに行う事務や事業の財源に充てるため森林環境譲与税として配分されます。
この税金は、2023年度末で期限切れとなる復興特別住民税の看板を掛け替えて、取り続けるもので、森林の吸収源対策や公益的機能の恩恵を口実に、国やCO2排出企業が引き受けるべき負担を、国民個人に押し付けるものです。
2019年から森林環境譲与税は自治体への交付が始まっていますが、交付基準の人口指標が高いことから、私有人工林がない都市部に多額に配分される問題等があります。
森林を有する自治体が、体制整備や森林整備に活用できるように交付基準を見直します。森林環境税・森林環境譲与税は、森林整備に安定的な財源確保策としてふさわしいのかと林業経営者からも疑義が示されています。安定的な財源である国の一般会計における林業予算の拡充を求めるとともに、需要のある自治体への地方交付税の拡充を求めていきます。
放射能汚染の継続的な調査をすすめる――東日本大震災の原発事故から14年、森林の除染は、住宅、農地の周辺部以外、除染されていないため、森林内の放射能セシウムの多くは土壌に分布しています。樹木の汚染は樹種や調査地点によって異なっています。汚染地域における適切な森林管理、安全な木材利用のため、放射能汚染の継続的な調査をすすめます。
国有林を国民の共有財産として持続的な管理経営にとりくむ――国有林は、国土面積の2割、森林面積の3割を占め、奥地山岳地帯や水源地帯に広く分布し、9割が保安林に指定され、国土・環境の保全や林産物の供給、山村地域の振興など国民生活にとっても重要な役割を担っています。
これらの役割を確実に実行していくため、国有林にかかわる情報や資料を公開し、事業の計画段階から、自治体・住民、国民との連携をはかり、地域の経済や雇用に配慮した、持続的な管理経営にとりくみます。 |
れいわ新選組
参院選2025マニフェスト
基本政策農林水産動物福祉
2 本物の安全保障
~戦争ピジネスには細担しない~
<防災>
●森林の適切な保全・管理で、土砂災害や洪水への防災力を高める。
そのための森林管理などの「緑の公共事業」と人員確保への予算を国が確保する
3 農林水産・動物福祉
●持続可能な林業
・森林や河川の整備、造林など「緑の公共事業」で地域の環境を保全し、雇用を創出する
・最先端の伐採用機器導入や調査などのためのデジタル化を促進し、林業の安全性を高めて地域の安定した雇用とする
・森林の計画的な伐採と、再造林(植林)率100%を目指すことで森林資源を保全する
・民有林活用による里山保全のための土地法制を整備し、森林保護を徹底する |
参政党
参政党の政策2025
森林を尊び、将来世代に希望を残す林業の実現
▶︎
現在の補助金に頼る、大量生産の自然破壊型林業を見直す。今こそ原点に立ち返り、「資源を使い続けること(持続性)を意識した環境創造型林業」を実現する。
主な施策
成長産業化を目指す政府の指針を転換し、林業の持続性を意識した長期的なビジョンを示していく。 欧米のフォレスターのように、林業従事者が憧れの職種となるよう、魅力の発信に努める。
また、林業従事者の公務員化を進め、山村地域の雇用創出、地域活性化につなげる。
林業を持続可能なものにするために、川上から川下までの情報の透明化により流通の無駄を省く。木材を適正価格で流通させ、資源を効率的に使用し利益を向上させる。山林所有者にも利益を適正配分させ、山林の所有権放棄を減少させる。
30by30を達成するべく、国で自然保護すべき地域の買い取りと管理を進める
▶︎生物多様性を回復し、より良い状態にしていく「ネイチャーポジティブ」の考え方をコンセプトにした「生物多様性条約」を日本も批准している。2030年までに地球上の陸地、海域の30%を保護区域にするという数値目標、いわゆる「30by30」を世界196の国と地域と共に掲げているが、未だ陸域で20.5%、海域で13.3%に留まっている。
主な施策
30by30達成に向け、積極的に私有地を国で買い取り、自然保護区化を進める。
企業や地域社会の取り組みに対し、「自然共生サイト」として認定する環境省の制度を評価し、適正に推進していく。 |
保守党
日本保守党の重点政策項目
7.エネルギーと産業政策
(日本の優れた省エネ技術の活用。過度な再エネ依存の見直し)
29.
農林水産行政の抜本的見直し(就業人口の増大と増産、国内産品の国内消費の強力推進) |
社会民主党
過去の選挙の各政党政策リストの中の森林林政策
各党の森林政策ー参議院選挙2022各党政策から(2022/7/15)
総選挙2021各党の政策の中の森林林業政策(2021/10/15) (2021/10/22訂正)
各党の森林政策ー参議院選挙2019各党政策から(2019/8/15)
総選挙2017各党の政策と森林林業政策(2017/11/25)
参議院選挙2013各党のマニフェストから (2013/7/27)
総選挙のマニフェストと森林林業(2012/12/25)
参議院選挙2010各党マニフェストから (2010/7/18)
参議院選挙各政党マニフェスト森林政策部分 (2009/8/15)
参議院選挙と各党の森林林業政策 (2007/8/12)
kokunai6-73<saninsen2025>
|