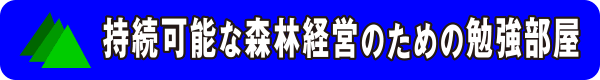 |
| 生物多様性を高める林業経営と木材利用ー今年度の森林・林業白書から(2025/7/30) | |||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||
|
森林・林業白書についてはネット上に詳しいサイトがあり、令和6年度 森林・林業白書(令和7年6月19日訂正)、以下のデータがダウンロードできる丁寧なページがあります(全文、概要版、参考資料、紹介された事例)。 左が目次です。 今年の白書の特集は「生物多様性を高める林業経営と木材利用」です。 「生物多様性が白書のテーマとなるのは、初めてです。」冒頭担当者の説明がありました。「エー本当?!」びっくり。 前出の概要編の内容を中心に丁寧な説明があたので、その中の特集jの内容と、どして今の時点で生物多様性が取り上げらられたのか、日本の森林政策の中での生物多様性の位置づけの変遷などを紹介します。 特集ページを中心に紹介します。 (特集「生物多様性を高める林業経営と木材利用」の構成)
順番に見て行きます 生物多様性とは、で始まる(1)生物多様性とその意義。生物多様性とは林野庁の関連ページに掲載されているようなことが、記載されていて新しいことはありません。 でも、その節に、森林の有する多面的機能と生態系サービスというサブ節があり 「?森林・林業基本法においては、国土の保全、水源の涵養、地球温暖化の防止、林産物の供給等の森林の有する多面的機能の持続的な発揮が国民生活及び国民経済の安定に欠くことができないものと位置付け。こうした多面的機能は、国際的には生態系サービスと呼ばれている」という記述があります。 2001年に出来た「森林・林業基本法」では、森林の持っている多面的機能の中に生物多様性という言葉が例示されていない、ということに気が付きました。 林野庁は、森林の多面的機能の中で生物多様性を位置づけていますが、それはいつか、この点は大切なので後述します。 (2)の生物多様性をめぐる近年の動きも、国際的、国内的、民間企業の動きをフォローしていますがあまり新しい指摘ありありません(概要版2ページ、本体版6−7ページ) (2.我が国の森林における生物多様性とこれまでの保全の取組)
(2)我が国の森林における生物多様性保全の取組の経過:として、「明治時代以降、森林の荒廃に対する伐採等の行為規制から始まった森林の保護に関する施策は、生物多様性の概念も取り込みながら、保全管理・利用までを含む施策へと深化」とまとめています。概要版5ページ。明治以降保護林などの伐採規制,が始まったときには、生物多様性保全というコンセプトがなかったのは間違えありませが、1915年に設定された国有林の保護林制度などが我が国の我が国の自然保護の先駆的な役割を果たしたと指摘しています(本文13ページ) (3)生物多様性保全に関する具体的な施策 ーーーーー まとめのセッションの構成は以下の通り (1)概要版P10には、「林野庁では2024年3月に、これまでの生物多様性保全の実践例も参考にしつつ、生物多様性を高めるための林業経営の在り方を示すことを目的として、「森林の生物多様性を高めるための林業経営の指針」を取りまとめ、? 指針は「生物多様性への負の影響を回避し、機能の低下した森林の再生を通じた生物多様性の回復を図ることも含め、生物多様性の保全に一層配慮した森林管理を実践することにより、多様な動植物の生育・生息空間としての森林の質を現状より高めること」を強調」とっいった、記述があります。
そして、マーケットとの連携をツールとして、森林経営計画書に生物多様性に関する記述が出来るように取組事項記載されるようになったことが、記述されています。 以上です 最後に記載されているような、林野庁の新たな制度「令和6年に林野庁がとりまとめた森林の生物多様性を高めるための林業経営の指針を踏まえ、生物多様性保全の取組に係るPDCAサイクル実施を森林経営計画の作成を通じて行うことができるよう、令和7年3月に計画書の様式を見直しました。」 そうなんですね。林野庁がガバナンスの中心に据えている森林経営計画制度の中に、しっかり生物多様性事案が取り組める、しっかりした提案を昨年度い行い、今年度から施行!!なのですね。 これらのことが今年度の白書の特集が「生物多様性を高める林業経営と木材利用」となった理由(の一つでしょう (森林・林業基本法と、森林林業計画のなかの生物多様性) 前述したように、2001年にできた、森林林業基本法の第2条(森林の有する多面的機能の発揮)には以下の記述があります 第二条 森林については、その有する国土の保全、水源のかん養、自然環境の保全、公衆の保健、地球温暖化の防止、林産物の供給等の多面にわたる機能(以下「森林の有する多面的機能」という。)が持続的に発揮されることが国民生活及び国民経済の安定に欠くことのできないものであることにかんがみ、将来にわたつて、その適正な整備及び保全が図られなければならない。 つまり、基本法の記述では、森林の有する多面的機能の中に、生物多様性の保全機能は入っていないません。(、等の中に入っています。) それでは、基本法に基づき、5年に一度作成されて森林・林業基本計画の中ではどうでしょう。 一番新しい2021年作成された森林林業基本計画の冒頭以下の記述があります 基本計画前書きの冒頭 2021年の記述では森林の多面的機能の中に生物多様性保全はいっている!が、2001年の基本法には入っていません。 ということで、基本計画の歴史の中を見てみました
以上基本計画の前書き部分だけ、具体的な記述内容を見てきました。 2001年の基本計画にも「はじめに」はありませんが、次のページ「第1 森林及び林業に関する施策についての基本的な方針」の中に「近年は、地球温暖化問題や自然との共生のあり方への関心の高まりから、二酸化炭素の吸収源・貯蔵庫や生物多様性を保全する場としての森林の役割などを含めた多面的な機能の発揮が一層期待されるようになっている」とあります。 林業基本法が、森林・林業基本法となったタイミングが森林政策の一部に生物多様性保全というコンセプト位置づけられた時点であること間違えないでしょう。 そして、生物多様性基本法が2008年にできて、2011年森林・林業基本計画あたりから、生物多様性保全の記述が多様となり、、COP10等を契機に、2009年林野庁内に森林における生物多様性保全の推進方策検討会などができて、施策が定着してきたということでしょう ーーー kokunai5-6<R6hakusyo> |
|
■いいねボタン
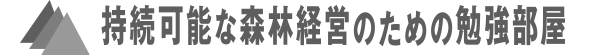 |